ナレッジ
2024.4.22

近年、製造業においてトレーサビリティの重要性が高まっており、適切にトレーサビリティを取ることが取引の条件になる場合もあります。その背景には、従来よりも高い品質管理や不良品流出時の迅速な対応と影響の低減、また環境対応などが必要になっていることが挙げられます。
しかし、トレーサビリティは自社だけで完結しない場合が多いため、関係会社との連携が必要です。この記事では、トレーサビリティの概要や種類、製造業でトレーサビリティが必要とされる理由について解説を行います。
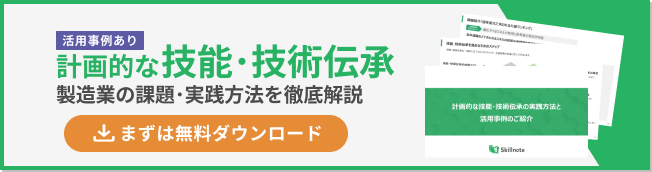
目次
トレーサビリティとは、製品やサービスの提供に関するサプライチェーン全体の各工程において、そこで使われる物品などを追跡可能な状態に落とし込むことです。
特に製造業におけるトレーサビリティでは、製品に使われる原材料や部品の調達、加工や組み立てなどの生産、流通や販売に至るまでの仕入れやこれらの業務に関わる担当業者を記録し、追跡可能なシステムを構築します。
トレーサビリティにおいては、トレースバックやトレースフォワードという用語が使われます。時系列を遡って部品や製品の動きを確認することがトレースバック、時系列に沿って追跡することがトレースフォワードです。
また、トレーサビリティは主に、チェーントレーサビリティと内部トレーサビリティの2種類に分類されるため、それぞれについて解説します。

チェーントレーサビリティとは、原料の調達から加工や組み立てなどの生産、物流、販売までを、1つの企業内部だけでなく複数の企業にまたがってトレーサビリティを管理するものです。一般的にトレーサビリティと表現されるものは、チェーントレーサビリティのことをさしているものが多いです。
チェーントレーサビリティを構築することで製造に関わる事業者は、自社が製造する製品にどこで作られた部品や原料が使われているかを確認できます。また、自社で製造した部品がどこに納入され、最終的にどのような製品になっているのかも確認できます。
チェーントレーサビリティの実施には、サプライチェーンに関わる各企業が深く連携することが重要です。自社内で適切に情報を取得管理し、それをサプライチェーンの企業に共有する仕組みを作る必要があります。
各企業のトレーサビリティに関する理解や取組の内容、価値観などに差があるとうまくいかないため、チェーントレーサビリティを構築するにはサプライチェーン全体での頻繁なコミュニケーションと認識合わせが必要不可欠です。

内部トレーサビリティとは、ある企業内など特定の範囲に限定して部品や製品の移動を把握するような取組です。
複数の原料や部品によって構成されるある製品の内部トレーサビリティでは、各原料、部品が入荷した際の履歴や各工程での加工内容に加えて、製品完成後の検査内容やその結果、また完成品の納入先などを管理します。
製品を構成する要素以外にも、製品を製造する過程で用いる工具や治具などが内部トレーサビリティには必要です。
ただし、内部トレーサビリティを構築するために、それまで不要だった作業が現場で必要になる場合があります。不要だった作業は生産効率を下げることに繋がる可能性があるため、上位主導のトレーサビリティ取得は反発が起きることもあるでしょう。
そもそも、役に立たない情報を取得・管理する対象としないことは当然として、きちんとコミュニケーションを取り、お互い納得した上で取り組むことが、内部トレーサビリティの構築において重要なポイントです。
製造業では、他の業界と比べても品質管理や業務効率化の観点で、トレーサビリティが重要視されています。その具体的な理由を4つ紹介します。
製品の製造に関するトレーサビリティを適切にとっていれば、製造した製品の検査工程などで不具合が確認された場合にも、速やかに対策を取ることが可能です。
不具合品に使われていた部品はいつ製造されたものか、その部品を加工した時の工具は何だったのかなどを確認していくことで、原因の究明が可能です。また、ピンポイントで対策を取ることで、その後の品質向上に繋がります。
自工程では抽出できず、後工程になってはじめて影響が判明するような不具合の場合には、トレーサビリティが取れていないと原因究明に時間がかかります。その結果、不良品の流出防止に繋がってしまうため、注意が必要です。
関連記事:品質保証と品質管理の違いとは? 仕事内容、連携、スキルアップ方法について解説
万が一、市場で不具合が発生しリコールしなければならない状況に陥った場合でも、トレーサビリティがしっかりと取れていれば早急な対応が可能です。
まずは影響範囲を明確にし、速やかに対策を立てつつ顧客へ影響が及ばないように動く必要があります。トレーサビリティにより、不具合が発生する可能性がある製品がいつ作られたもので、現在どこにあるのか、誰に販売したかの特定がスムーズです。
また、リコール対象を適切に限定することにも繋がります。複数のロットで作られた部品が混流している場合、製品ごとにトレーサビリティが取れていなければ本来は問題のないロットの製品を切り分けられずに回収対象とせざるを得ません。
このように、トレーサビリティが取れていることで、回収対象の特定、選別が用意になるため、数量を限定しつつ必要な顧客に対してのスムーズな対応が可能です。
イメージが付きにくいかもしれませんが、トレーサビリティを取れるようにすることで、工場のスマートファクトリー化やDXが大きく進む可能性があります。
例えば、トレーサビリティを取得するためのバーコードやRFIDによるデータ収集、管理はスマートファクトリー化に向けて効果的な取組です。また、トレーサビリティに関する情報の信頼性を高めるために役立つブロックチェーン技術はDXに繋がるかもしれません。
このように、トレーサビリティの実現を目指す過程で、スマートファクトリー化やDXに関する技術開発や認知も進んでいくでしょう。
関連記事:スマートファクトリーとは? 意味や目的、メリットを解説
トレーサビリティを取ることは、近年多くの製造業で求められているカーボンフットプリントの測定にも効果的です。ある製品の製造から廃棄に至るまでに排出される温室効果ガスを測定する中で、特に原料採取から販売に至るまでの過程では、トレーサビリティが役に立ちます。今後は、カーボンフットプリントの観点から、部品の調達要件にトレーサビリティが適切に管理・運用されていることという条件が加わる可能性もあります。
製造業でのトレーサビリティに関する取り組みをイメージするために、具体的な事例を2つ紹介します。多くの企業が適用可能な事例なので、もし実施していない場合には参考にして頂ければと思います。
従来、画像検査を行う際にデータを取得・保存していましたが、検査結果と検査時の画像データを紐づけることはしていませんでした。トレーサビリティとして、検査結果と検査時の画像を紐づけ長期保存することで、後から振り返る必要があった際に検査結果の妥当性を判断しやすく、検査精度の向上にも繋がります。
従来、部品製造時に部品に対して刻印を行うのはロットナンバーのみで、ロット内の個々の識別はできない状況でした。そこで、より精度の高いトレーサビリティを実現するために、レーザー印字により製品ごとにシリアルナンバーを刻印することにしています。
その結果、同一ロット内でも生産順が明確になり、使用部品のトレーサビリティを確認できます。これは、不具合発生時の原因究明においても重要な役割を担うでしょう。
トレーサビリティは、特に製造業において不良品の流出防止など品質管理面、また環境対応の面で重要な役割を担っています。しかし、トレーサビリティをうまく取ることは難しく、サプライチェーンを構成する企業や社内関係者との連携が必要不可欠です。
「技術伝承」をシステム化するなら「Skillnote」!
●スキルデータの活用で「技術伝承」の解決策がわかる
●自社に最適化したスキルマップがかんたんに作れる
●「品質向上」に成功した事例を大公開
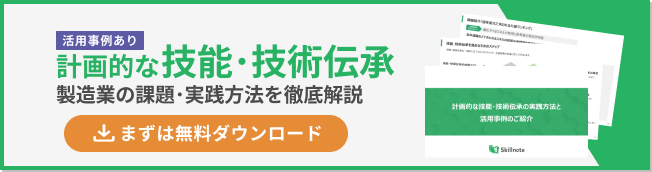
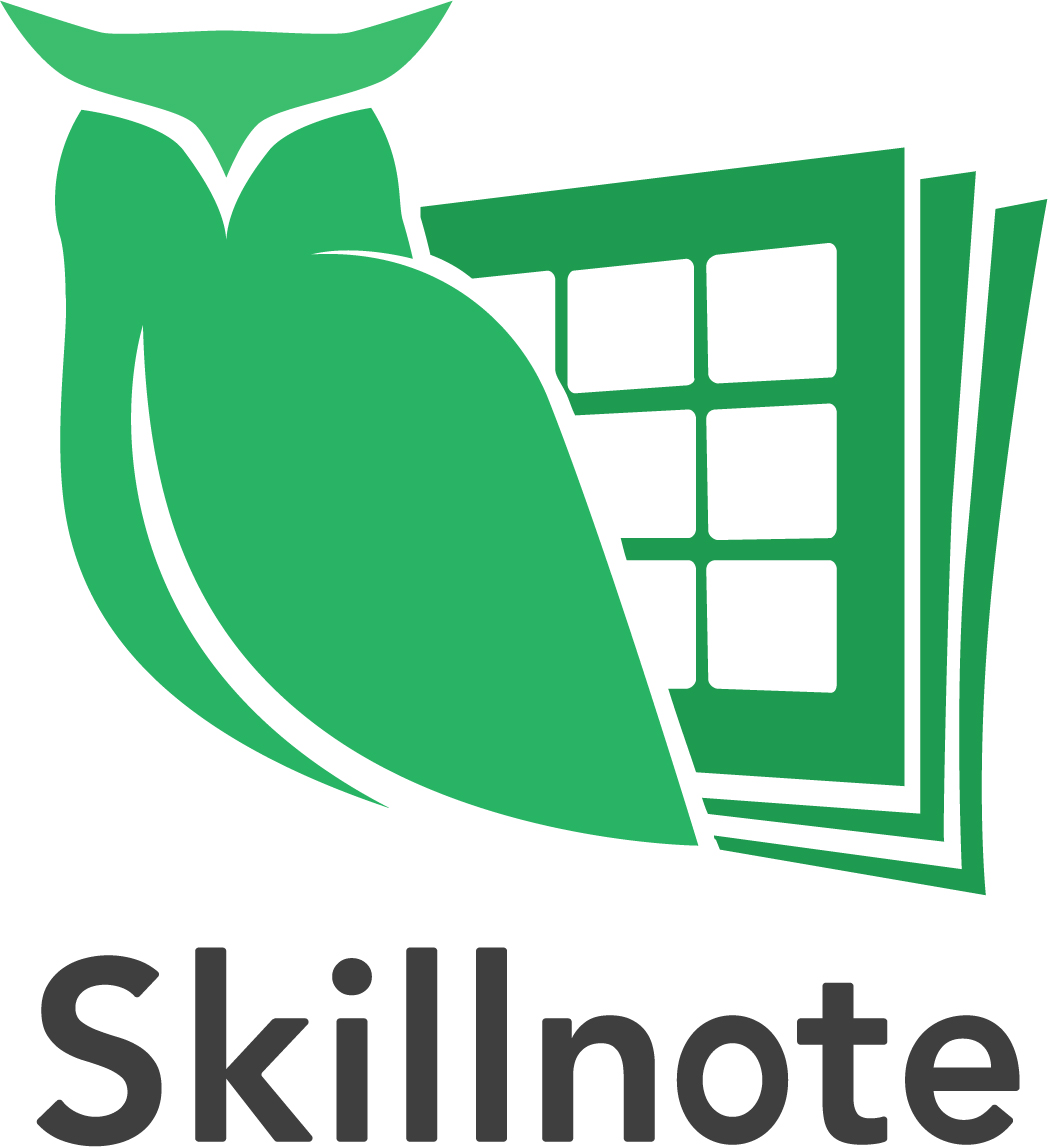
スキルマネジメントMagazineは、人材育成や生産性・品質向上など、スキルマネジメントに関するお役立ち情報をお届けし、人がいきいきと働き活躍することをサポートするメディアです。

ナレッジ
2024.4.18

ナレッジ
2024.4.18
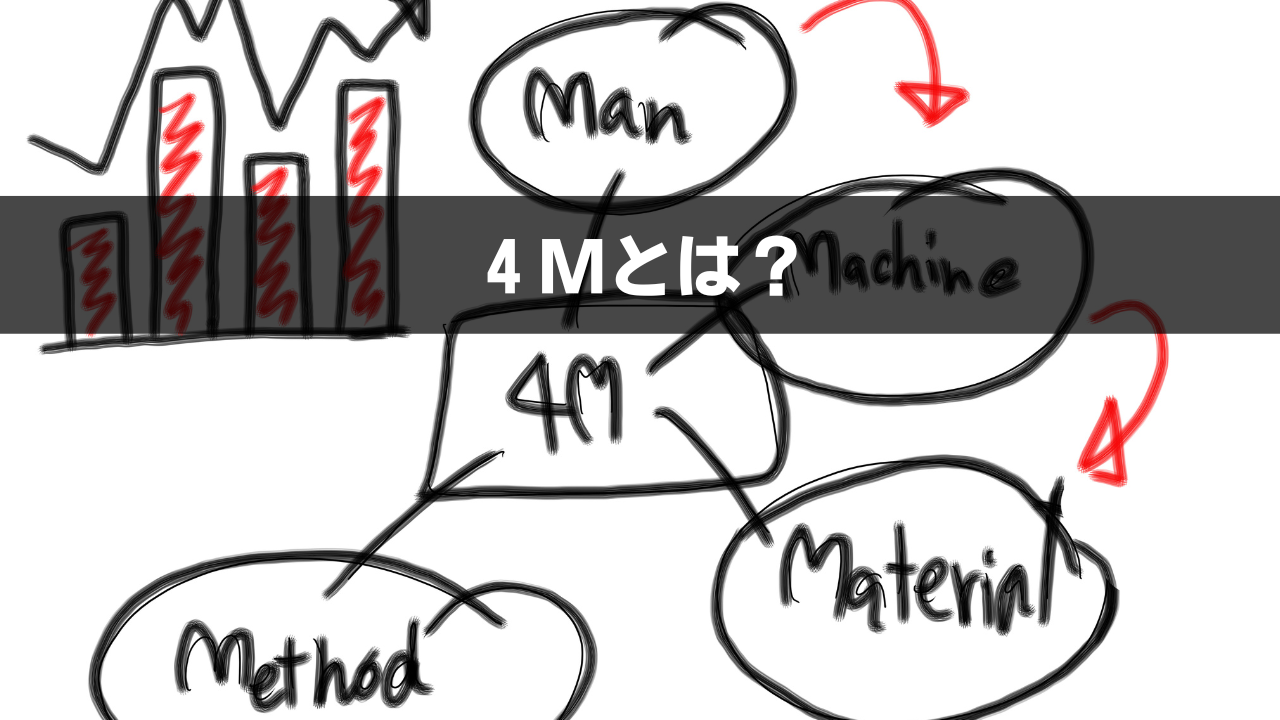
ナレッジ
2024.4.18

ナレッジ
2024.4.19

ナレッジ
2024.4.19

ナレッジ
2024.4.19

