ナレッジ
2024.6.17

製品やサービスの品質を確保するために、国際規格であるISO9001やIATF16949の品質マネジメントシステムにおいてFMEA(故障モード影響解析)は重要な役割を担っています。
しかし、いざFMEAを作成しようとすると、故障モードの抽出をどのようにすればいいか、困ることが多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、FMEAにおける故障モードについて、適切に抽出を行うことの重要性や抽出時の注意点、また参考にできる故障モードの一覧や事例を紹介します。

目次
FMEAにおいて故障モードとは、製品や工程の故障状態を引き起こす構成部品・構成要素の破壊やミスなどをさします。
故障モードを考える対象は設計FMEAと工程FMEAで異なっており、設計FMEAでは製品を構成する要素である部品を対象として故障モードを抽出します。一方で工程FMEAでは、部品以外の構成要素も含めて故障モードの抽出が必要です。
具体的には、工程の構成要素である5M、設備、作業者、材料、方法、計測の5つについて、それぞれが持つ故障モードを抽出しなければなりません。部品の故障モードに比べて、作業者や材料の故障モードはイメージしにくいため、過去実績のある情報をうまく活用することが重要です。
ここで、適切に故障モードを抽出できていないと、製品や工程が持つ重大な故障状態を見逃すことに繋がる可能性があります。場合によっては大きな事故に繋がってしまう形もあるため、FMEAにおける故障モードは、抜け漏れなく確実に抽出しなければならない重要な要素の一つです。
関連記事:【解説】FMEAとは?期待効果と注意点について解説します。
FMEAを作成するにあたって、故障モードを抜けもれなく抽出するのは簡単ではありません。そこで、まずはここで紹介する注意点を考慮しながら、故障モードを抽出してみるといいでしょう。
FMEAにおける故障モードを初めて抽出する場合には、「故障」や「不良」と混同してしまいがちです。しかし、これらは明確に区別をする必要があります。
「故障」は、故障モードが要因となって発生する製品や工程の機能障害を意味します。例えば、自動車が走行できない状態や製造工程が停止してしまっている場合は故障しているといえます。
「不良」は故障ではなく、そもそも狙い通りの設計が実現できていない場合や作業者への指示が間違っている状態により、期待する機能を実現できていない状態を指します。
これらは、故障モードと明確に区別する必要があり、抽出する故障モードの中に故障や不良が紛れ込んでしまわないような対策が必要です。もっとも効率的な選択肢は、FMEAの作成経験があり故障モードの抽出、判断ができる人に協力してもらうことでしょう。
FMEAで故障モードを抽出する際には、抽出の対象となる部品の粒度を合わせることが重要です。例えば、構成部品表で同じ階層になる構成部品の粒度で合わせるなどをすると、イメージしやすいでしょう。
故障モードを抽出する対象の粒度が合っていないと、製品の構成要素を抜け漏れなく抽出できているかの判断が難しくなります。また関係者でレビューをする際に、レビュアーが理解しにくく違和感を持った状態になってしまうため、本質的な議論に入るのが遅くなってしまいます。
細かい構成要素まで含めて故障モードを抽出、解析する必要がある場合には、あらかじめ作成した大きな粒度のFMEAと紐づけた状態で、新たなFMEA帳票を作成するといいでしょう。
製品や工程の構成要素である、部品や5Mの故障モードは、網羅的に抽出する必要があります。
FMEAでは、各解析対象の故障モードが発生した際に生じる影響の厳しさや故障モードの発生頻度、故障状態の検出のしやすさに応じて、適切な処置を行います。仮に抽出できなかった故障モードが重大な影響を引き起こしてしまう可能性がある場合、本来設計段階で取るべきだった対策が取れません。
その結果、製品が市場に出荷されたり、実際に工程が稼働し始めたりしてから該当の故障モードが発覚し、重大な事故を引き起こしてしまいます。製品のリコールなどに繋がり、消費者に影響を与えると共に、会社経営にも大きなダメージを与えてしまうため、網羅的な故障モードの抽出は必要不可欠です。

網羅的な抽出が必要な不可欠なFMEAの故障モードですが、初めてでも自身だけで簡単にできるものではありません。そこで、参考にできる一般的な故障モードの一覧や多くの製品に使われる代表的な部品の故障モード事例を参考にすると、抜け漏れが発生しにくいでしょう。
まずは、一般的な故障モードの一覧表から、FMEAを行う対象に当てはまる故障モードを抽出するといいでしょう。
表1:FMEAで考慮すべき一般的な故障モード一覧

これらは、主に設計FMEAの際に故障モードとして当てはまることの多い項目です。まずは、この表の項目に当てはまるものを抽出し、その上で他に故障モードはないかを考えると効率的に抽出できるでしょう。
ここでは、代表的な電子機器について、どのような故障モードが想定されるのかを紹介します。電子機器を構成要素とした製品を扱っている場合には、参考になるでしょう。
表2:代表的な電子機器の故障モード

機械系の機器を扱っている場合には、次のような故障モードが参考になるでしょう。
表3:代表的な機械系機器の故障モード

工程FMEAでは、人の作業における故障モードも抽出する必要があります。ただし、設計FMEAのように決められた故障モードを抽出することは困難なため、ここでは故障モードに繋がる要因を紹介します。
表4:代表的な人の作業における故障モードの要因

故障モードを抽出する際には、これらの要因によってどのような故障モードが引き起こされるかを考えるといいでしょう。
FMEAの目的を果たすためには、製品や工程の構成要素の粒度を合わせること、それぞれの構成要素に対して故障モードを網羅的に抽出することが必要不可欠です。各構成要素の故障モードを網羅的に抽出するのは簡単ではないため、今回紹介したような一覧表や事例をうまく活用するといいでしょう。故障モードの抽出を効率化でき、精度の高いFMEAの作成に繋がります。
「Skillnote」でISO力量管理業務を圧倒的に効率化!
●バラバラだったスキルや教育訓練記録をシステムで一元管理
●ペーパーレス化の実現によって共有もラクラク
●スキルと教育が紐づいて運用の手間がなくなる

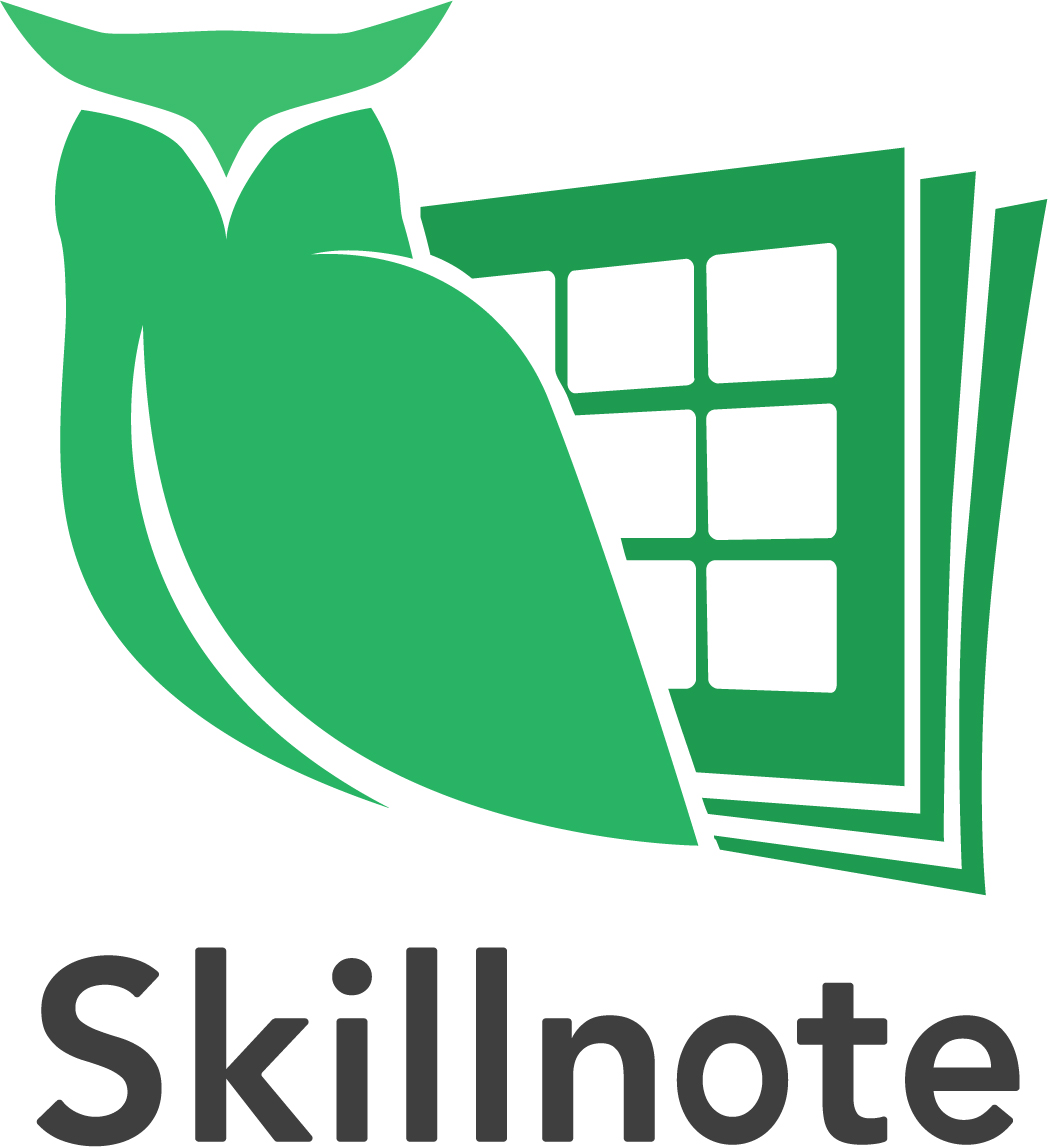
スキルマネジメントMagazineは、人材育成や生産性・品質向上など、スキルマネジメントに関するお役立ち情報をお届けし、人がいきいきと働き活躍することをサポートするメディアです。

ナレッジ
2024.6.17

ナレッジ
2024.4.23
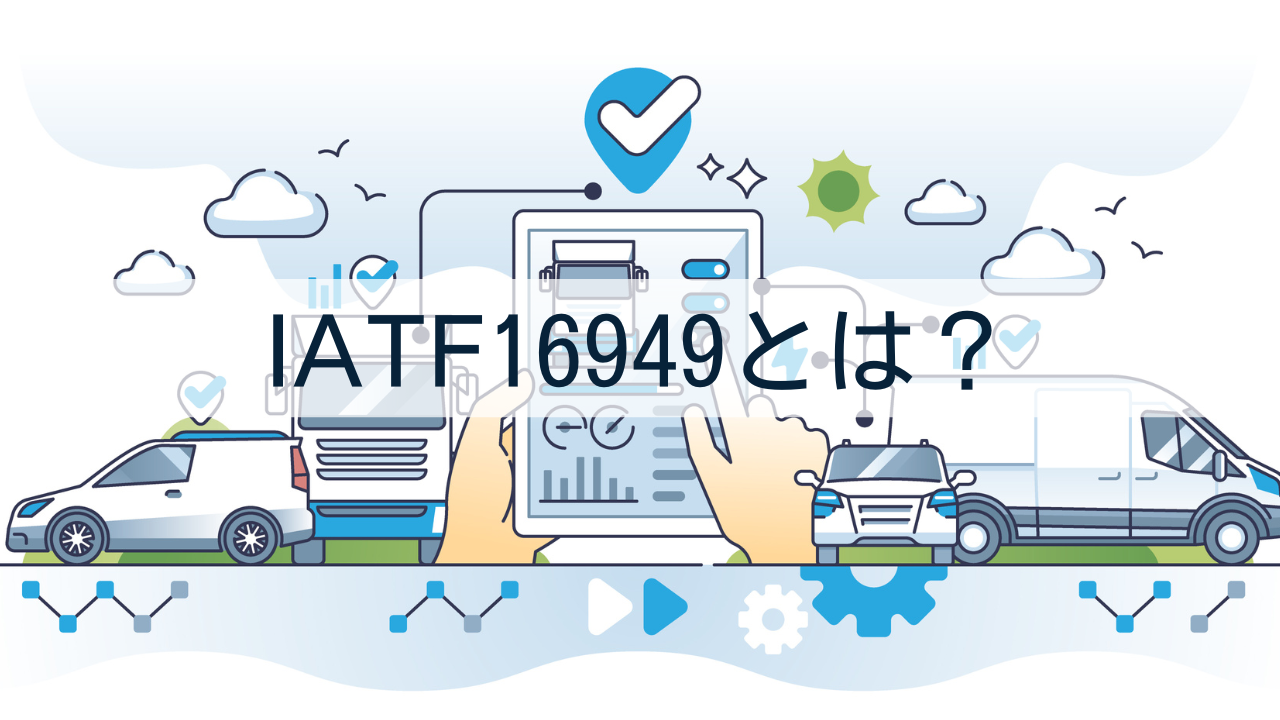
ナレッジ
2024.6.17

ナレッジ
2024.4.24

ナレッジ
2024.4.18
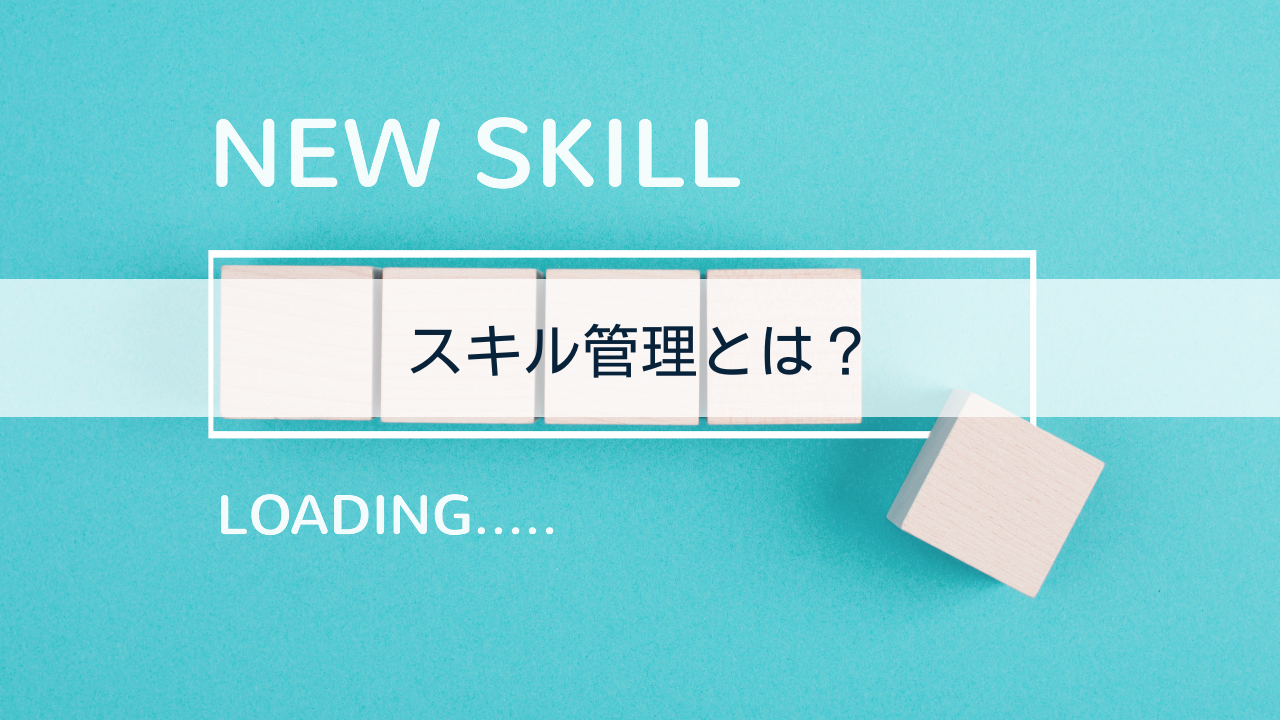
ナレッジ
2024.6.19

